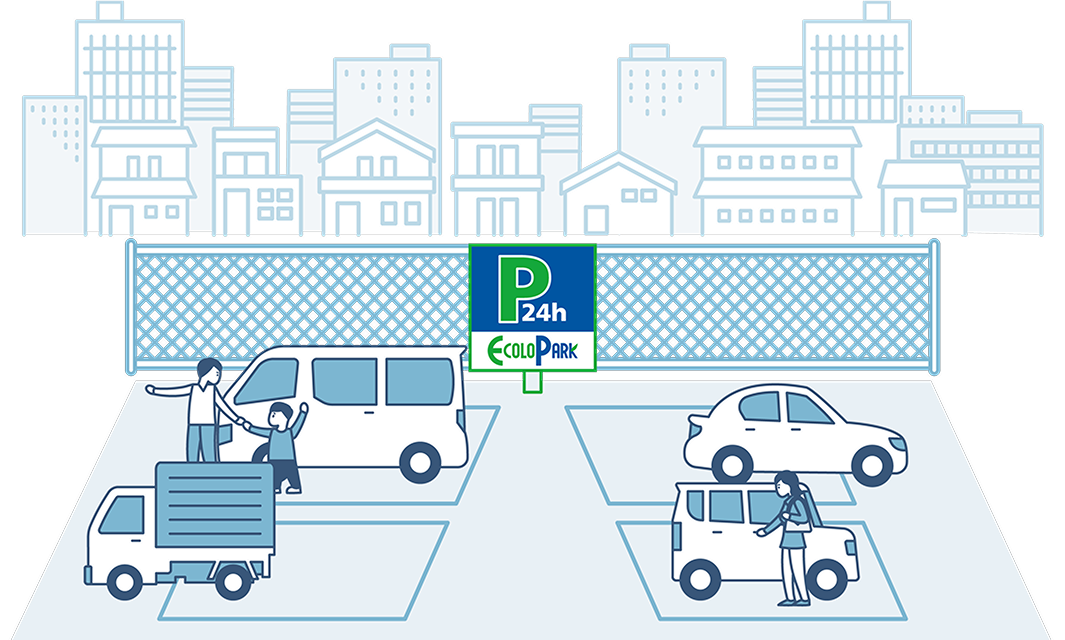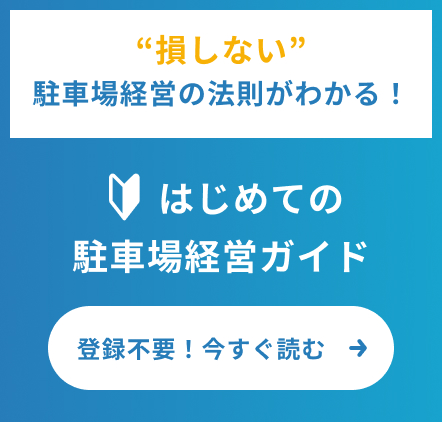コインパーキングや駐車場経営のよくあるトラブル事例と対処方法を紹介

駐車場経営とは?コインパーキング経営や一括借り上げ方式など運営スタイルの違いを解説
駐車場経営は、土地を活用して安定した収益を得られる方法として注目されています。建物を建てるより初期投資が少なく、狭小地や変形地でも始められる点が魅力です。
しかし、ひと口に駐車場経営といっても、経営形態や運営方式には複数の選択肢があり、それぞれに特徴やメリット、デメリットがあります。オーナー様が安心して収益を得るためには、自分の土地に合ったスタイルを選ぶことが大切です。
ここでは、代表的な経営形態と経営方式について解説していきます。
駐車場経営の2つの経営形態|コインパーキング経営・月極駐車場経営
駐車場経営には大きく分けて「コインパーキング経営」と「月極駐車場経営」の2種類があります。
コインパーキング経営は、使用した時間に応じて利用者から料金を徴収する形態です。短時間利用や来客用の需要が高いエリアでは収益性が高く、料金設定を柔軟に調整できる点が魅力です。一方で、利用者数が立地に大きく左右されるため、需要の少ない場所では安定収入を得にくい面もあります。
月極駐車場経営は、利用者と1か月単位で契約する形態です。契約期間中は安定した収入が得られるのがメリットですが、空車が出ると収益が減少するリスクがあります。地方や住宅街などでは需要に応じて月極駐車場経営が有利になるケースが多く、地域性を考慮して選ぶことが重要です。
駐車場経営の3つの経営方式|個人経営方式・管理委託方式・一括借り上げ方式
次に、駐車場経営を運営する方式には「個人経営方式」「管理委託方式」「一括借り上げ方式」の3つがあります。
個人経営方式は、オーナー様が自ら料金回収や清掃、設備管理を行う方法です。自由度が高く手数料もかからない反面、手間やリスクが大きく、専門知識や時間が必要になります。
管理委託方式は、専門の運営会社に清掃や料金管理など一部業務を委託する方法です。オーナー様の負担を軽減できる一方、委託料が発生するためオーナー様の収益はやや減少します。
一括借り上げ方式は、運営会社が土地を一括で借り上げ、オーナー様には毎月固定の賃料が支払われる仕組みです。空車リスクやトラブル対応をすべて会社が負担してくれるため手間や管理に時間をとられることなく、安定した収益を求めることが可能です。
特に、初めて駐車場経営を始めるオーナー様にとって安心感が大きく、人気の高い選択肢となっています。
コインパーキングから出られない?故障時の料金は無料になる?駐車場経営のトラブル事例と原因を紹介
駐車場経営は少額投資で始めやすい一方、設備不具合や表示の分かりにくさが原因で苦情が発生することがあります。
国民生活センターのPIO-NET集計では、時間貸し駐車場(コインパーキングを含む)の表示に関する相談が2013〜2018年度で1,731件(2017年度は363件)寄せられました。料金表示の誤解や精算周りの不満が典型で、看板・精算機付近の表示の分かりにくさが背景にあります。
また駐車場内事故は全体事故の中で無視できない規模で、交通事故分析センター統計(H28)では「駐車場等」で18,766件(全体の約3.8%)でした。設計・運用面の配慮はオーナー様の収益保全にも直結するため注意が必要です。
参照:「コインパーキングの表示をしっかり確認しましょう」国民生活センター
参照:「駐車場の交通事故減少に向けた安全性向上のための施設運用に関する研究」日本メディア教育開発センター
駐車場機器の故障:精算機の故障によって料金が未清算になってしまうケース
精算機の紙幣・硬貨処理や釣銭機構の不具合は出庫遅延や苦情につながります。国民生活センターの公表事例には「お釣りが出ない」「規約掲示が小さく見えにくい」等の相談が記録されており、表示の明確化と機器の定期点検が重要です。
苦情やクレーム:騒音や狭さ、清掃の不十分が原因で利用者による苦情がくるパターン
区画の狭さは車体同士の接触不安を生みやすくなります。実際、標準的な条例・指針でも普通車マスは概ね幅2.5m×奥行5.0m以上が例示されていますが、設計段階から基準値を踏まえ余裕寸法を確保し、清掃・照明・掲示の基本品質を維持することが苦情抑制につながるでしょう。
精算ミス:誤った駐車番号を入力してしまい、別の車両の料金を支払ってしまう事例
番号入力方式の駐車場では他車室番号の誤入力が一定割合で生じます。消費生活相談でも「表示・規約の分かりづらさ」がトラブル要因として繰り返し指摘されており、車室番号の分かりやすさの向上、案内標識の追加、精算前の番号を再確認することを促す画面表示が有効です。
駐車スペースからのはみ出し:車両サイズや停め方の影響で車体が枠からはみ出してしまうケース
最近の普通車は全幅1.8m級が一般的で、2.5m幅の車室でもドアの開閉の余裕が不足しやすくなります。標準条例・指針の寸法例(普通車2.5m×5.0m以上)に加え、混在する大型車への配慮として一部マスの拡幅や通路幅の余裕設定を検討すると安全性と満足度が高まります。
駐車券が入らない:駐車券の折れや汚れ、機械の読み取り不良で正しく挿入できないパターン
公的な統計資料では駐車券の読取不良の発生率そのものは公表が限られていますが、公的相談事例には「駐車券紛失時の高額精算」「表示方法の不備」など、駐車券・精算周りのトラブルが確認できます。駐車券の保管や取扱い注意を掲示し、駐車券なしでも遠隔対応や入退場ログで照会できる運用整備が望まれます。
駐車場から出られない:ロック板やゲートの故障により精算後も場内から出られなくなる事例
ロック板(フラップ)は、無断出庫防止のため駐車後に路面から板が上がり、精算することで下降して出庫できる装置です。東京都消費生活総合センターでは、ロック板が車体に当たった・上がったまま出庫し損傷した等の相談事例を公表しています。入出庫時の確認と注意表示の徹底が非常に重要になってきます。
参照:「コインパーキングの上手な利用方法 」東京都の消費生活情報
一方、ロック板に頼らない「ロックレス」方式もありますが、こちらは過去調査で市場全体のごく一部にとどまっており(2017年時点で約1%)、現在も多くの現場でロック板が主流です。信頼性の確保には定期点検と停電・通信障害時の代替手順(遠隔解錠、非常連絡)の整備が不可欠になるでしょう。
専門家や警察に相談するのはあり?コインパーキングや駐車場経営のトラブル対処法&予防策について
駐車場経営は比較的シンプルな土地活用に見えますが、実際には機器の故障や利用者の誤操作、不正駐車や騒音など、思わぬトラブルが発生することがあります。
こうした問題を放置すれば利用者の満足度が下がり、オーナー様の収益や信用にも影響しかねません。
そこで重要となるのが、日常的な予防策の徹底と、トラブル発生時の的確な対処法です。監視カメラや看板の設置、定期点検に加え、専門家や警察への相談を視野に入れることで、安心して経営を続けられる体制を整えられます。
ここでは、主にコインパーキングや駐車場経営のトラブル対処法と予防策について紹介していきます。
監視カメラの設置:不正駐車や不法投棄の証拠を記録し、抑止力につなげる
駐車場は死角ができやすく、不正駐車・投棄・破損行為が起きやすい環境です。防犯カメラは映像証拠の確保に加え、犯罪や違反行為の抑止効果が学術的に証明されています。
駐車場・駐輪場での設置前後を比較した研究では、通報件数の大幅減やゴミ投棄・落書きの減少が示され、利用者の不安低減にも寄与しました。設置に際しては、プライバシー配慮(撮影範囲・掲示)と、夜間の必要照度を満たす機材選定(RBSS等のガイド)を意識すると実効性が高まります。
RBSSとは優良防犯機器認定制度のことで、防犯カメラや照明機器などの防犯設備について、一定の性能基準や認定要件を満たしているかを評価・認定する制度です。こうした基準を参照することで、客観的に信頼性の高い機材を選定できるようになります。
看板の設置と工夫:利用者ルールや注意点を明示して、誤操作や苦情を防ぐ
料金体系・最大料金の適用条件・精算手順・緊急連絡先などは、入口や精算機の周り、場内の要所に複数掲示すると利用者の誤解を防げます。実際に消費生活相談では「表示が分かりづらい」「想定外の高額精算」などの事例が継続的に報告されており、読めるサイズ・配置・用語統一が重要です。
また、ピクトグラム(文字だけではなく絵や記号を使うもの)や番号再確認の促し(例:〈車室番号を再確認〉)を加えると、誤った番号の入力も減らせます。
定期点検:定期的にメンテナンスを行い故障や事故を未然に防ぐ
精算機・発券機・ゲート・ロック板などの機器は、年数が経つと紙幣の読取、釣銭、センサー、通信系統に不具合が生じやすい部分です。そのため点検では「動作/通信」「消耗品・ユニット」「停電時の保安照明・非常手順」をセットで確認します。
国土交通省によると、駐車場の照度や設備安全(滑り止め・車止め・排水等)といった運用基準を整理しており、夜間視認性・安全動線を満たす維持管理が推奨されます。停電時は保安照明10lx以上の確保や、ゲートの手動解錠・対応の手順を常日頃整備しておくと、出庫不能の二次障害を防げます。
専門家による無料相談の利用:法的・運営面のリスクを把握し、的確な対策が打てる
料金表示や精算トラブルは、消費生活センターでの相談事例が一定数蓄積されており、表示の改善や苦情の対応に関する助言が得られます。
設計・安全面に関しては、各自治体が公表する「駐車場設計・施工指針」等の基準に沿って、区画寸法・車路幅・照度・案内表示の適否を事前チェックすることが有効です。
犯罪や迷惑行為の抑止設計(見通し・照明・カメラ・人の目の導線)については、警察の犯罪予防環境設計(CPTED)関連資料も参考になります。
駐車場経営は儲からない?失敗例とリスク回避方法を解説

駐車場経営は建物投資に比べ初期費用を抑えやすい一方、立地選定や設計・運用を誤ると収益が伸びず「儲からない」と感じやすい分野です。
国土交通省の「駐車場設計・施工指針」や「まちづくりと連携した駐車場施策ガイドライン」には、車室寸法・動線・安全対策といった基本要件を示しており、これらに基づく計画が収益性と利用者満足の土台になります。
本文では失敗例を整理し、根拠に基づく回避策を提示していきます。
需要のない立地で赤字に:事前に周辺の駐車ニーズを調査することで回避
赤字の典型は「需要の薄い場所」での開業です。駅やお店、オフィスが近くにあるかどうかや、周辺の駐車場が足りているか、昼間に人が多く集まるかや・滞在時間などの需要を把握せずに始めると、空車が慢性化してしまう危険性があります。
駐車場をどこに作るかを考える時は、その地域のまちづくりの方針や交通ルールを踏まえて駐車需要をどう捉えるか(たとえば建物に駐車場をつける義務があるかや地域の交通政策、路上と駐車場内の役割分担)まで確認しましょう。ガイドラインは、都市の施策に合った駐車場配置や料金の決め方についての考え方がまとめられています。
競合参入で利用者が激減:差別化をはかり強みを活かす
好立地でも競合他社が増えると稼働率は分散します。そのため単純な値下げは消耗戦になりがちなので、まずは「停めやすさ」と「安心感」を設計で担保することがいいでしょう。
普通車の車室は概ね幅2.5m×長さ5.0m以上が実務の目安で、動線・車路幅・視認性(照度・標識)を合わせて最適化します。安全配慮(車止め・防護施設・転落防止装置)やバリアフリー配慮、夜間照度の確保は、利用者がまた使いたいと思える快適さにつながる差別化要素になります。
さらに、通常料金・最大料金・精算手順・緊急連絡先などの掲示は「読める大きさ・適所への掲示」が重要です。国民生活センターでは、最大料金の条件の誤解や駐車券の紛失時の高額精算等の相談事例を公表しており、分かりにくい表示がトラブルを誘発する実態を指摘しています。
看板の用語の統一や文字サイズ、設置位置の工夫で誤解を減らし、苦情の対応コストを抑えましょう。
事故で損害が発生:防犯カメラやロック板、保険の加入でリスクを最小限に抑える
駐車場は「安全施設」(安全のための設備)の有無で事故リスクが変わります。交通事故総合分析センター(ITARDA)の資料や関連レポートでは、駐車場内での事故の発生状況が整理されており、人と車がすれ違う時の動きの特徴や駐車場内での事故の規模が確認できます。
これらは駐車場内の通り道の設計や見通しの良さ、照度の明るさや案内表示の必要性を証明しています。
また、無断出庫防止のためのロック板(フラップ)は事故防止に有効ですが、停電時や機器不良時に出庫不能となるリスクもあるため、定期点検と非常手順(遠隔・手動解錠、保安照明)を整備しましょう。国交省の設計関連資料では駐車場内での事故を防ぐために必要な設備やルールがまとめられています。たとえば、転落を防止する仕組みや安全柵・明るさの確保の安全要件を示し、夜や緊急時の対応の重要性を示しています。
コインパーキング経営を始める方必見!失敗しない駐車場運営会社の選び方
駐車場経営では、運営会社の選び方が成功の鍵になります。最新の国土交通省の「駐車場マネジメント推進ガイドライン」(2025年5月)では、民間事業者にも質を伴う対応が求められており、実績・対応力・管理内容・費用の透明性などが運営会社の評価の重要な基準とされています。
参照:「持続可能なまちづくりと都市交通の実現に向けた駐車場マネジメントの推進のためのガイドラインの公表」国土交通省
ここでは、これらの最新の動向を踏まえたうえで、運営会社の選び方のポイントを4つ解説します。
対応力とサポート体制:クレームやトラブルに迅速、丁寧に対応できるか確認
事故統計を見ると、2023年度中に駐車場で発生した事故は14,865件で、車両の相互事故が61.1%、人対車両事故が31.5%、車両単独の事故が7.4%という構成でした。
この数字は、トラブル対応力がどれほど重要かということの一つの指標になり得ます。運営会社には、24時間いつでも対応可能なのか、緊急時の対応マニュアルは整備されているかを必ず確認しましょう。
管理内容の柔軟性:清掃・点検・料金設定など必要な業務の確認
「駐車対策の現状」に関する最新資料(2025年1月発行)では、地方公共団体の駐車場整備計画において、整備を設置した後の維持管理や、料金設定を見直せるような柔軟な仕組みが必要だとされています。
清掃をする頻度や設備の点検、案内表示の改善などを迅速に対応してくれる会社であれば、利用者の満足度とそれに伴う収益を維持しやすくなるでしょう。
費用の透明性:オーナー様と管理会社間で確認すべき管理費や追加費用
国土交通省のガイドラインで示される「適切な料金表示」に関する要件には、料金制度を見える化することが含まれており、利用者だけでなくオーナー様と管理会社間でも契約時の費用の明細が明確であることが推奨されています。
契約書にて「管理費」「清掃費」「点検費用」「追加メンテナンス費用」などが明記されているか、請求サンプルを見せてもらえるかなどを確認しましょう。
駐車場経営を始めるのに一括借り上げ方式コインパーキング経営がおすすめな理由!6つのメリットを紹介
駐車場経営は、建物投資に比べて初期費用を抑えられる点や、短期間で収益化しやすい点から人気の土地活用方法です。
しかし、経営方式によってはオーナー様が負うリスクや手間は大きく異なります。近年、国土交通省が公表した「まちづくりと連携した駐車場施策ガイドライン(第2版)」では、都市交通政策と連動した駐車場運営の重要性が示され、民間事業者が主体となる柔軟な運営手法の必要性が強調されています。
また、2025年1月に公表された「駐車対策の現状」でも、需要変化や都市構造に対応するために持続可能な運営方式の導入が課題とされており、その解決策の一つとして「一括借り上げ方式」が注目されています。ここでは、その6つのメリットを詳しく紹介します。
契約期間のペナルティがない:柔軟な契約で安心して始められる
契約に縛られることを不安に感じるオーナー様は少なくありません。その点一括借り上げ方式では、契約期間満了時に違約金や高額な解約料を設けないケースが多く、オーナー様のライフプランや地域事情の変化に応じて柔軟に契約を見直せます。
将来的に土地を売却したい、別用途に転用したいといった場合にも安心です。
狭小地でも対応可能:駐車場一台から始められて早期収益化ができる
一括借り上げ方式では、1台分といった狭小地でも効率的に運営できるため、遊休地を放置するリスクを避けつつ収益化することができます。特に、住宅地に点在する未利用地や、建物を建てるには狭い土地でも有効に活用できます。
トラブル対応をお任せ可能:クレームや機器の故障対応を全て運営会社が代行
駐車場経営で最もストレスが大きいのは、現場で発生するトラブル対応です。精算機の紙幣の詰まりやロック板の作動不良、利用者からのクレーム対応などは、オーナー様一人で行うには大きな負担となります。
さらに2023年の統計によれば、全国で14,865件もの事故が駐車場で発生しています。
こうした現場対応を運営会社に一任できるのが、一括借り上げ方式の強みです。オーナー様は本業に集中しながら安定収益を得られます。
少額の初期投資:建物不要で簡単な設備投資でスタート可能
建物建設には数千万円以上の投資が必要ですが、コインパーキングは舗装と精算機、ロック板やゲートなどの最低限の設備で始められます。
初期費用を数百万円程度に抑えられるため、短期間で投資回収が可能です。また、舗装や精算機はリース契約を活用できる場合もあり、資金負担をさらに軽減できます。
管理負担が少ない:清掃や点検などオーナー様の手間がほとんどかからない
一括借り上げ方式では、日常的な清掃、機器の点検、除草や照明点検といった作業をすべて運営会社が担うため、オーナー様の手間は最小限で済みます。
特に遠方に土地を所有している場合、維持管理を任せられる点は大きな安心材料となるでしょう。
安定した収益:空車リスクを気にせず毎月決まった額の賃料が振り込まれる
一括借り上げ方式の最大の魅力は、稼働率に関わらず固定賃料が保証される点です。近隣に競合が出現したり、一時的に需要が落ち込んでも、オーナー様には毎月一定額の収入が確保されます。
これは、安定収益を求めるオーナー様にとって大きな魅力です。
コインパーキングや駐車場経営のトラブルでお悩みならエコロパークにお任せ
駐車場経営は少ない初期投資で始められる点が魅力ですが、実際には精算機の不具合やロック板の故障、利用者からのクレームなど、思わぬトラブルがつきものです。
しかし、こうした問題に適切に対応できなければ、利用者満足度の低下や収益悪化につながり、オーナー様にとって大きな負担となってしまいます。
エコロパークは、そのような不安を抱えるオーナー様に最適な解決策を提供しています。特に一括借り上げ方式に強みを持ち、清掃や定期点検、機器の修理対応、さらにはクレーム処理までを一貫して代行します。
加えてオーナー様には毎月安定した賃料が支払われるため、空車リスクや突発的なトラブルに悩まされることなく、安心して土地を運用できます。
また、エコロパークは狭小地や遊休地の活用にも柔軟に対応しています。1台から始められるプランを用意しているため、土地の広さにかかわらず早期に収益化を実現できる点も大きな魅力です。
さらに監視カメラの設置や夜間照明の確保など、安全性の高い運営体制を整えているため、利用者にとっても安心して利用できる環境を提供しています。
駐車場経営を「安心して、安定的に」続けたいと考えるオーナー様にとって、エコロパークは心強いパートナーです。トラブル対応をすべて任せられる体制と、確実な収益を得られる仕組みによって、土地活用をスムーズに成功へ導いてくれます。
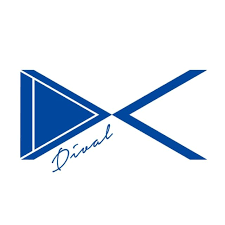
監修者
ディバルコンサルタント株式会社 代表取締役
明堂 浩治
芝浦工業大学 工学部 建築工学科卒。大手建設会社(大成建設グループ)にて、個人・法人地主への土地活用提案や建築営業に20年間従事。その後独立し、ディバルコンサルタント株式会社を設立。新築・改修工事、建物管理、土地の有効活用提案まで一貫したサポートを提供しており、特に相続後の土地や建物の活用相談にも多数の実績を持つ建築・不動産コンサルティングの専門家。
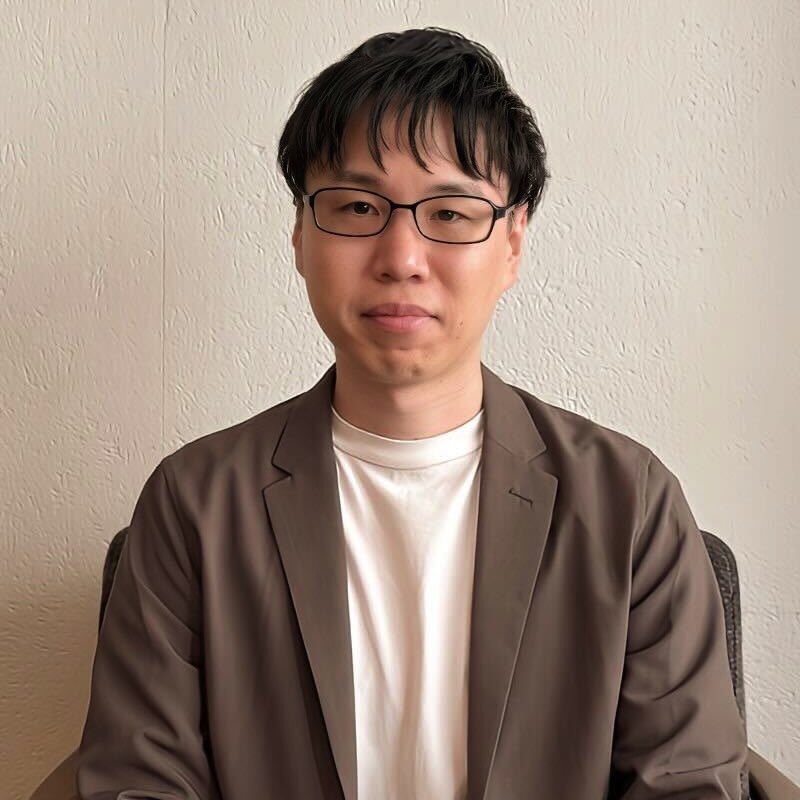
執筆者
株式会社スタルジー 代表取締役
飯塚 祐世
タワーマンションの理事長として、サブリース方式で空きが出ていた駐車場の収益改善に取り組み、修繕積立金不足の課題を解決。現在は、マンション管理組合向けの実践的サポートサイト「管理組合サポート」を運営し、現場目線での課題解決を行う。実体験に基づいた土地・建物の収益改善提案を得意とする、管理と経営に強い実務家。