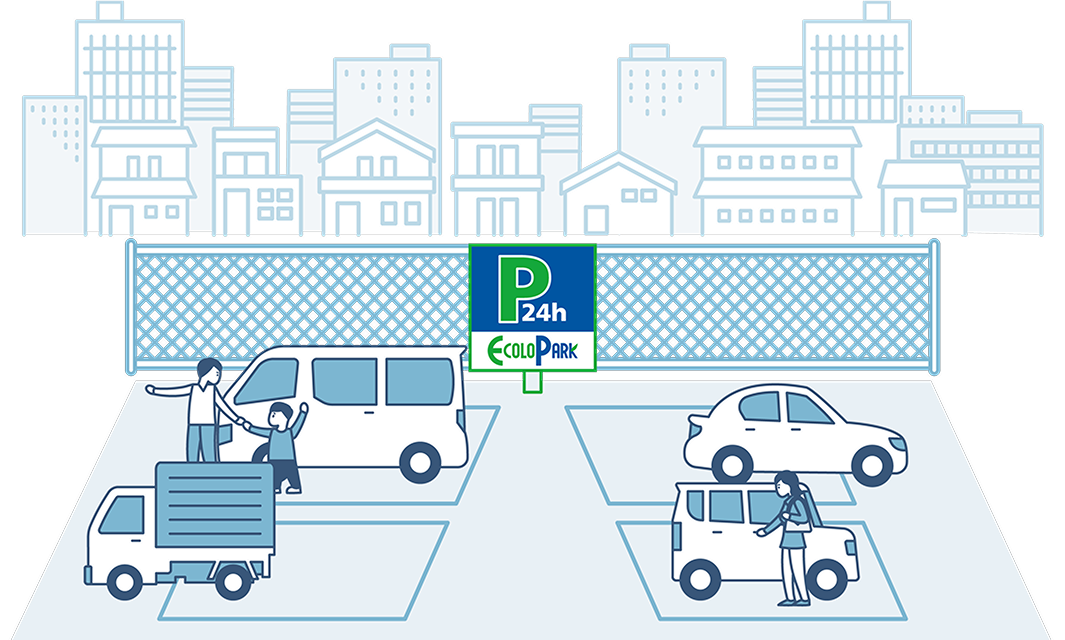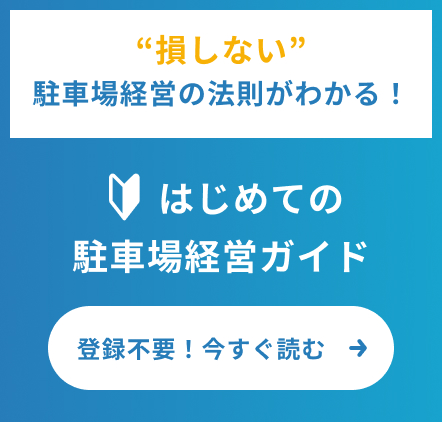農地活用で儲かる方法は?収益化可能なビジネス事例と相談方法を紹介
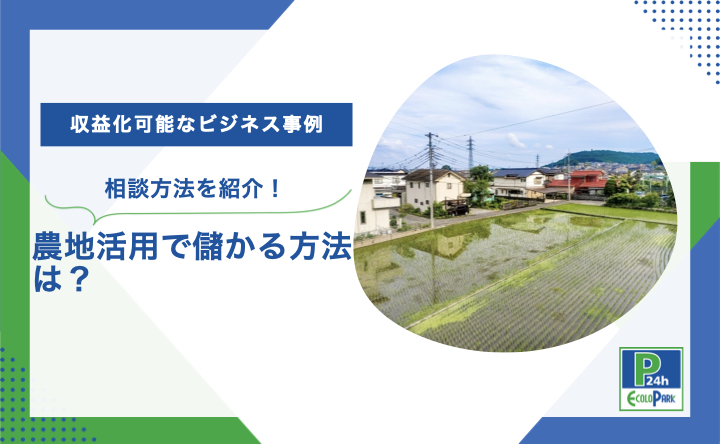
農地とは何か?農地の特徴・種類・法律上のルールや転用できる農地とできない農地を解説
農地とは、農作物の栽培を目的とした土地を指し、農地法第2条では「耕作の目的に供される土地」と定義されています。
たとえ現在耕作していない土地でも、登記上の地目が「田」や「畑」であれば農地と見なされ、法律に基づく制限を受けます。農地の活用には、まずその区分や種類、適用される法律を正しく理解することが重要です。
参考:農地法
転用できる農地とできない農地の違い|白地農地・市街化区域内農地
農地を他の用途に転用できるかどうかは、その農地がどの「都市計画区域」にあるかによって大きく変わります。
都市計画区域とは、街の発展や土地利用をルール化するために国や自治体が定めた区域で、「市街化区域」と「市街化調整区域」に大別されます。
たとえば、市街化区域内の農地は、今後住宅や商業施設が集まることを前提とした地域にあるため、比較的転用しやすいのが特徴です。農業委員会の許可(農地法第5条)を得ることで、住宅地や駐車場、店舗などへの転用が可能になります。
一方、市街化調整区域にある農地は、街の広がりを抑えるためのエリアであるため、原則として建物の建設や用途変更が厳しく制限されています。
特にこの区域の中でも農業振興地域に指定された「青地農地」は、農地として保護されており、転用はほぼ不可能です。例外として、公益性の高い施設(保育園や防災施設など)の場合は許可が下りるケースもあります。
なお、市街化調整区域の中でも「白地農地」と呼ばれる土地は、農業振興地域には含まれておらず、比較的転用許可が得やすいとされています。
白地農地は、同じ調整区域内でも使い道の幅が広く、駐車場や資材置き場などとして活用されるケースも増えています。
農地の種類を紹介|遊休農地・耕作放棄地
農地の中には、長期間にわたり耕作が行われていないものもあります。こうした土地は大きく分けて以下の2つに分類されます。
- 遊休農地
一時的に耕作されていない農地で、将来的には再び農業に利用される可能性がある土地です。所有者が農業を再開する意思を持っていることもあります。 - 耕作放棄地
過去1年以上耕作されず、今後も耕作の見込みがないとされる農地です。農林水産省の「農業構造動態調査」(令和4年)によると、耕作放棄地の面積は約42万ヘクタールに達しており、全国の農地の約1割を占めています。
農地活用に関する法規制とは?|農地法・都市計画法
農地を活用するには、主に2つの法律が関わってきます。
- 農地法
農地の売買、賃貸、転用などを規制する法律で、原則として農業委員会の許可が必要です。特に転用を伴う場合は、目的や所在によって知事または農業委員会の許可を要します。 - 都市計画法
都市計画法とは、国土交通省や都道府県、市区町村の管轄下である町づくりに関するルールを定めた法律です。都市計画区域内で農地を転用する際には、この法律も関わってきます。たとえば、市街化調整区域では建築物の新築や土地の用途変更が厳しく制限されており、転用の審査に通るには難しいことなどが挙げられます。
これらの法規制は、農地の無秩序な開発を防ぎ、農業の継続と地域の秩序ある発展を目的としています。したがって、農地の活用を検討する際には、まず土地の区分や法的制限を確認し、必要に応じて専門家や自治体に相談することが重要です。
農地活用は儲かる?活用することで得られる4つのメリットについて
農地を放置していると、固定資産税などの維持費だけがかかり、活用されないまま資産価値が下がるリスクもあります。しかし、正しい方法で農地を活用すれば、収益化や節税につながる可能性が十分にあります。
ここでは、農地活用によって得られる代表的な3つのメリットをご紹介します。
収益が得られる|特に一括借り上げ方式の駐車場経営なら毎月安定した収益を得ることが可能
農地を活用することで、最も大きなメリットはやはり「収益化」です。特に注目されているのが一括借り上げ方式による駐車場経営です。
この方式では、専門業者が土地をまとめて借り上げ、オーナー様に毎月一定額の賃料を支払います。
この仕組みにより、オーナー様は運営リスクを負うことなく、安定した収入を確保できるのが大きな特徴です。
コインパーキングの運営会社が設備投資や運営・管理まで全て行ってくれるため、初めての方でも安心して始められます。月に数万円、年間で数十万円以上の収益を得ている事例も多く、耕作をやめた農地の有効な活用方法として注目されています。
農地にかかる税金負担を軽減できる|固定資産税で払う分以上の利益が見込めることも
農地のまま耕作をしていない状態でも、所有していれば毎年固定資産税がかかります。
農地の固定資産税は、宅地や事業用地と比べると安く設定されていますが、それでも100坪程度で年間3〜5万円程度の税金が発生することもあります。農業をしていない限り収入はゼロのため、いわば「赤字の資産」となってしまいます。
一方で、この農地を駐車場として転用すると、地目が「雑種地」などに変更され、固定資産税は数倍に跳ね上がる可能性があります。
たとえば、100坪の土地で年間10〜20万円前後になるケースもあります。ただし、月額5万円で貸し出せば、年間60万円の収益が見込めるため、税負担を差し引いても40万円以上の手元利益が残る計算になります。
つまり、確かに税金は上がるものの、活用次第ではその支出を上回る収益が得られるため、実質的には土地が「コストのかかる遊休地」から「利益を生む収益資産」へと転換できるのです。
加えて、コインパーキング経営を一括借り上げ方式で採用すれば、空車リスクや運営負担もなく、収支の見通しを立てやすい点も安心材料となります。
土地活用でお悩みなら、お気軽にご相談ください
農地の資産価値が高まる|使われてる土地は市場価値も上がりやすい
農地は活用されていないと、雑草や荒廃が進み、見た目の印象も悪くなります。こうした土地は市場価値も低く評価され、買い手も見つかりにくくなる傾向があります。
一方で、駐車場やトランクルームなどとして活用されている土地は、継続的に収益を生む「稼働資産」として評価されやすくなり、資産価値が上がります。
買い手や借り手が見つかりやすくなるだけでなく、地域からも「有効に活用されている土地」として好意的に受け止められます。
土地を相続しやすくなる|活用することで売却や分割がしやすくなり相続しやすくなる
農地を相続する際には、「誰が管理するのか」「どう分けるのか」といった問題で親族間のトラブルに発展することが少なくありません。
特に活用されていない農地は、資産価値や活用方針が不明確であるため、相続時の判断が難しくなる傾向があります。
しかし、すでに収益化されている農地であれば、資産価値が明確で分割・売却の判断がしやすくなり、相続人同士の意思決定もスムーズになりやすいのが特徴です。また、相続税評価額も土地の用途によって変わるため、早めに活用方針を定めておくことは、節税対策としても有効です。
農地を放置するとどうなる?考えられる4つのデメリットについて
農地を所有しているものの、活用する予定がないまま放置している方も少なくありません。しかし、農地をそのままにしておくことは、多くのリスクやデメリットを伴います。ここでは、農地放置によって生じうる4つの代表的な問題について解説します。
害虫・害獣による資産価値の低下
管理されていない農地は、草木が生い茂りやすくなり、ネズミ・イノシシ・ハクビシンなどの害獣や、ハチ・蚊といった害虫の住処となります。特に雑草が伸び放題の土地は、害虫が大量発生しやすく、周辺住民から苦情が寄せられることもあります。
このような状態が続くと、近隣との関係が悪化するだけでなく、土地自体の資産価値も低下します。「見た目が悪い」「衛生面に問題がある」といった評価を受けることで、売却や貸し出しも困難になってしまうのです。
不法投棄・不法侵入などの犯罪の温床化
人の目が届かない農地は、不法投棄や不法侵入といった犯罪のターゲットになりやすいです。たとえば、粗大ゴミや産業廃棄物を勝手に捨てられる事例は全国で多数報告されており、一度投棄されると撤去には高額な費用が発生します。
さらに、空き農地は無断で車両を停められたり、住み着かれたりするケースもあり、トラブルが深刻化することもあります。放置状態のままでは、「使っていない=自由にしてよい」という誤解を生みやすく、犯罪の温床になりかねません。
相続時に親族同士で揉める原因となる
農地を相続する際に、活用実績がなく収益もない土地だと「誰が管理するのか」「どう分けるのか」で親族間の意見が食い違いやすくなります。
実際に、土地の相続トラブルは全国的に増加傾向にあり、特に地方の農地をめぐる争いは珍しくありません。
使われていない土地は資産価値が不明確で、現金のように簡単に分割できないため、感情的なもつれを生みやすいのです。反対に、活用している土地であれば収益の分配も可能となり、相続手続きもスムーズに進みやすくなります。
営農放棄によるペナルティや行政指導の対象になる可能性
農地を長期間耕作せずに放置していると、「遊休農地」「耕作放棄地」として認定され、市町村や農業委員会から指導や調査の対象となることがあります。
場合によっては、農地中間管理機構への強制的な貸付対象とされたり、農地法に基づく行政指導が行われるケースもあります。ここで出てくる農地中間管理機構とは別名「農地集積バンク」とも呼ばれ、使われていない農地を借り受けて必要とする農業者に貸し付ける仕組みを持つ機関のことです。
さらに、農地を放置していると「利用意向がない」と見なされ、将来的な農地転用の許可が下りにくくなる可能性もあります。つまり、いざ活用したいと思っても自由に使えなくなるリスクを孕んでいるのです。
使わない田んぼや畑をお持ちの方必見!農地を放置する以外の選択肢と注意点を徹底解説
農地を持ってはいるものの、耕作する予定がない、管理が負担になっているという方も多いのではないでしょうか。
ただ放置するだけでは、資産価値の低下や税金負担などのリスクがつきまといます。そこで、ここでは農地を「放置せずに活かす」ための4つの選択肢と、それぞれに伴う注意点をご紹介します。
別の用途に活用する:農地法に基づく転用許可や整備費用が必要
農地を住宅や駐車場、太陽光発電などの別用途に転用するには、農地法第5条に基づく許可が必要です。特に市街化調整区域内の農地では許可が厳しく、農業委員会や都道府県知事の審査をクリアする必要があります。
また、転用後に整地や舗装といった初期整備が必要になるため、費用負担も一定程度発生する点に注意が必要です。ただし、一括借り上げ方式の駐車場などであれば、業者が整備を含めて対応してくれるケースもあり、オーナー様の負担は軽減されます。
農地中間管理機構(農地集積バンク)を活用して貸し出す:貸出期間が長期になる場合がある
農地を活用する一つの手段として、「農地中間管理機構(農地集積バンク)」に登録して、農業者に貸し出す方法があります。これは国が推進する制度で、使われていない農地を集約・再利用する仕組みです。
メリットとしては、農地法の許可を得やすく、契約手続きも比較的スムーズである点が挙げられます。ただし、貸出期間が10年以上の長期になる場合もあるため、柔軟に土地を活用したい方には不向きな可能性もあります。
必要とする人に農地を売却する:農地法の許可が必要になる
農地を手放す選択肢としては、第三者への売却もあります。近隣の農業者や、農地を必要とする法人に売ることで、維持管理や税金負担から解放されるというメリットがあります。
ただし、農地の売買には必ず農地法第3条の許可が必要です。売却先が農業を目的としていなければ許可が下りないこともあり、自由な取引が制限される点には注意が必要です。農地を売りたい場合は、農業委員会や専門家に早めに相談しましょう。
農地を維持できない場合は手放す(寄付・還元など):手続きや費用が発生するケースがある
どうしても農地を維持できない場合は、自治体や国に寄付、あるいは所有権の還元を検討することも一つの手です。ただし、寄付は相手側の受け入れ条件が厳しく、必ずしも受理されるとは限りません。
また、農地の所有権を放棄する場合には、一定の手続きや費用(登記手続き・測量・分筆など)が発生するケースもあります。そのため、「手放す=すぐに負担がゼロになる」とは限らず、最終手段として慎重に判断する必要があります。
農地を放置せず、有効に使うことでリスクを回避しつつ、資産としての価値を維持・向上させることができます。それぞれの選択肢のメリット・注意点を理解し、自分の目的に合った方法を選びましょう。
専門家に相談するのもあり?農地を活用する前にするべきこと5選

農地を活用しようと考えたとき、すぐに何かの用途に転用できるとは限りません。農地にはさまざまな法的・物理的な制限があるため、事前準備を怠ると、計画そのものが実現できなくなる恐れもあります。ここでは、農地活用の第一歩として確認しておくべき5つのポイントをご紹介します。
土地の地目を確認する
まず最初に確認すべきは、登記簿上の地目が「田」「畑」などの農地になっているかどうかです。地目が農地である場合、農地法の制限を受けることになり、売買や賃貸、転用には原則として許可が必要になります。
地目がすでに「宅地」や「雑種地」となっている場合は、農地法の対象外となるケースもあるため、土地の登記事項証明書で正確に把握しましょう。
都市計画区域に当てはまるか確かめる
その土地が都市計画法上どの区域にあるかによって、転用の難易度や申請先が変わります。
たとえば、市街化区域にある農地は比較的転用しやすいのに対し、市街化調整区域内にある農地は、原則として建物の建築や用途変更が認められていません。転用の可否を左右する重要な情報ですので、必ず市区町村の都市計画課などで調べておきましょう。
農業振興地域か調べる
その農地が農業振興地域の中にあるかどうかも、転用の可否を判断する重要な要素です。この農業復興地域とは災害などで農業が難しくなった場所を支援するエリアのことです。この地域に指定されている場合、その土地は長期的な農業利用を目的としており、原則として転用は認められません。
ただし、一部には「除外申請」を出して転用できる可能性もあります。申請には時間と手間がかかるため、早めの確認と計画が不可欠です。
土地の面積・形状・接道をチェックする
土地の形状や広さ、道路への接道状況も、活用計画を進めるうえで欠かせない確認事項です。
たとえば、駐車場や太陽光発電に転用する場合、長方形で出入口が確保しやすい土地は活用しやすい一方、極端な変形地や傾斜地、接道がない土地は収益化に不利となる可能性があります。地図や現地調査による把握が大切です。
専門家や自治体に早めに相談する
農地の活用には、農地法や都市計画法、建築基準法など多くの法令が関係します。
自身で調べても限界があるため、早い段階で不動産や土地活用に詳しい専門家、あるいは市区町村の窓口に相談することをおすすめします。特に、転用許可や補助金の手続きは自治体によって対応が異なるため、事前のヒアリングが成功のカギとなります。
土地活用でお悩みなら、お気軽にご相談ください
農地を活用して収益化する方法|活用事例から見るビジネスモデルを紹介
農地をそのままにしておくよりも、何らかの形で活用し、安定的な収益を生む「資産」に転換する方がはるかにメリットは大きいです。
ここでは、実際に収益化が期待できる農地活用の代表的なビジネスモデル5つをご紹介します。初期費用・収益性・継続性のバランスを見ながら、自分に合った方法を検討してみてください。
駐車場経営:初期投資を抑えて手軽に始められる
最も手軽に始められる農地活用の一つが、駐車場経営です。
中でもコインパーキング経営による一括借り上げ方式を活用すれば、オーナー様は駐車場運営会社に土地を貸すだけで、毎月一定額の賃料を得ることができます。
舗装工事や精算機などの機器設置、管理業務もすべて業者が担うため、初期費用や維持管理の負担が大きく軽減されます。
国土交通省が公表した「令和4年度 駐車場整備状況等調査結果」によると、全国の時間貸し駐車場の整備台数は依然として増加傾向にあり、都市部に限らず郊外エリアでも設置が進んでいることが報告されています。
とくに住宅地や観光地、駅周辺などでは、短時間利用のニーズが安定しているため、地方の農地でも立地次第で十分に収益化が可能です。
このように、駐車場経営は立地や規模に応じて柔軟に対応でき、農地を低リスクかつ早期に収益化する手段として非常に有効です。
土地活用でお悩みなら、お気軽にご相談ください
トランクルーム経営:空調・電気設備不要な簡易型なら費用を抑えられる
農地を転用して物置型のトランクルームを設置する方法も、有効な収益化手段の一つです。特に空調や電気設備を必要としない「簡易型トランクルーム」は、初期費用を抑えられるうえに、郊外の住宅地などで一定のニーズが見込まれています。
矢野経済研究所が2023年に発表した「レンタル収納市場に関する調査」によれば、国内のレンタル収納市場は2022年度に約610億円規模となり、2027年度には730億円を超えると予測されています。これは、住宅の収納不足や災害備蓄ニーズの高まり、リモートワーク普及による空間確保需要などが背景にあります。
このように、成長産業であるトランクルーム事業は、農地の新たな活用先としても注目されています。設置スペースの確保や建築基準法の確認といった条件をクリアすれば、収益化は十分に可能です。
アパート・マンション経営:初期投資は大きいが、安定経営が可能
長期的に安定した収益を目指すなら、アパートやマンションを建てて賃貸経営する方法もあります。初期費用は高額になりがちですが、住宅需要が高いエリアであれば、家賃収入による堅実な収益が期待できます。
ただし、農地法だけでなく建築基準法や都市計画法の規制も関わるため、事前に専門家と連携して進める必要があります。相続対策や資産運用として検討されるケースも多く、都市部を中心に成功事例が多数あります。
太陽光発電用地:電力会社への売電収入が期待でき、国の支援制度も活用しやすい
再生可能エネルギー政策の一環として、太陽光発電用地への転用も人気があります。農地を「非農地」に転用したうえで、ソーラーパネルを設置し、発電した電力を電力会社に売電することで収益を得るモデルです。
資源エネルギー庁の発表によると、2023年度のFIT(固定価格買取制度)価格は10kW未満で16円/kWhとなっています。売電価格は下がりつつあるものの、今なお有力な活用方法として多くの農地で採用されています。
参考:資源エネルギー庁
ドッグラン:近年需要増のレジャー型活用で初心者も収益化可能
最近では、都市近郊や観光地での「ドッグラン」需要も高まっており、農地の平坦な特性を活かしてレジャー型施設として活用する例が増えています。特にペットブームの影響で、郊外型ドッグランの利用者数は拡大傾向にあります。
一般社団法人ペットフード協会の統計によれば、2023年の犬の飼育頭数は約727万頭。広い土地を必要とせず、簡易な柵や水道を整備すれば運営可能なため、初心者でも参入しやすい分野です。
農地の立地条件や周辺環境に応じて、適した活用方法は異なります。収益性だけでなく、初期費用や維持管理の負担、地域との親和性も含めて総合的に判断することが大切です。
知らなきゃ損!農地活用で使える補助金・支援制度を解説!
農地活用には整備や手続きなどに一定のコストがかかるため、自己資金だけで取り組むのは不安という方も多いでしょう。
しかし、国や自治体では農地の有効活用を後押しするため、さまざまな補助金や支援制度を整備しています。ここでは、農地活用に活用できる代表的な5つの支援制度を紹介します。
農地中間管理機構関連の支援(農地集積バンク)
農地中間管理機構(いわゆる農地集積バンク)は、遊休農地を必要とする担い手農家へ貸し出す制度で、都道府県が設置しています。この制度を通じて農地を貸し出すと、所有者には一時金や整備費の補助が支給されるケースもあります。
たとえば、農林水産省が実施する「農地中間管理事業推進事業」では、転用せずに貸し出す農地に対して一定額の支援が受けられ、放置農地の解消や地域農業の継続にも貢献できます。
農地次世代人材投資資金
農業を新たに始める若者や移住者に対して支給されるのが「農地次世代人材投資資金(経営開始型)」です。対象者には年間最大150万円が最長5年間支給される仕組みで、農地を貸し出す側にとっても「借り手がつきやすくなる」という間接的なメリットがあります。
この制度を活用する若年就農者は年々増えており、農地を貸す側としても早めに情報を提供しておくことでマッチングのチャンスが広がります。
地域創生関連の補助金
農地の活用方法によっては、「地方創生」「地域活性化」に関わる補助金が利用できる場合があります。たとえば、ドッグランや直売所、地域交流スペースなどの整備に対して、内閣府や地方自治体が支給する補助制度が多数存在します。
これらは自治体によって制度内容が異なるため、事業を企画する段階で早めに役所へ相談することが重要です。特に地域おこし協力隊との連携や農泊事業と組み合わせた提案は採択率も高まります。
小規模事業者持続化補助金
商工会議所や商工会を通じて実施されている「小規模事業者持続化補助金」は、農地を活用した事業(例:駐車場、トランクルーム、カフェなど)に対しても活用可能です。
補助上限は通常50万円ですが、特別枠では100万円以上になることもあり、広報・設備投資・WEB制作費用など幅広く使えるのが特徴です。農業法人化や地域ビジネスの第一歩としても活用されています。
太陽光発電設置時の再エネ関連支援
農地を太陽光発電用地に転用する場合、再生可能エネルギー導入を後押しする各種支援制度が活用できます。経済産業省の「再エネ導入加速化基金」や自治体の独自助成制度では、設置費の一部が補助対象となることがあります。
また、事業としての太陽光発電には「固定価格買取制度(FIT)」があり、売電価格が一定期間保証されるため、資金計画が立てやすくなります。2023年度の買取価格は10kW以上で11円/kWh(資源エネルギー庁)とされています。
このように、農地活用を始めるにあたっては、多くの公的支援制度が用意されています。条件や申請時期は制度ごとに異なるため、必ず最新の情報を各自治体や専門家に確認し、賢く活用しましょう。
農地活用に一括借り上げ方式コインパーキングでの駐車場経営がおすすめな理由
農地を収益化する方法の中でも、特に手軽でリスクの少ない選択肢として注目されているのが「一括借り上げ方式によるコインパーキング経営」です。
初期投資や運営の手間が少なく、確実な収入が見込めることから、農業を引退された方や相続で土地を取得した方にも人気の活用方法です。ここでは、その魅力を4つの観点から解説します。
初期投資のリスクを軽減できる
コインパーキング経営の一括借り上げ方式の最大の特長は、オーナー様が設備投資をほとんど必要とせずに始められることです。舗装や機器の設置、看板の設置など、通常であれば数百万円の初期投資がかかるところを、すべて運営会社側が負担してくれるケースがほとんどです。
そのため、資金面のリスクを抑えながら、収益化に踏み出すことができ「お金をかけずに土地を活かしたい」という方にとっては非常に魅力的な選択肢となります。
管理・運営がすべて業者負担で手間が省ける
コインパーキング経営の一括借り上げ方式では、運営・清掃・集金・クレーム対応といった管理業務もすべて運営会社が対応します。オーナー様が行うことは、基本的に契約と毎月の入金確認のみです。
特に農地のような広い敷地を自分で管理するのは大きな負担になりがちですが、この方式であれば完全に「手間いらず」で土地が活用されていくため、高齢の方や遠方に住む相続人にも好評です。
毎月安定した収益が見込める
コインパーキング経営の一括借り上げ方式では、毎月一定額の賃料が運営会社からオーナー様に支払われるため、収益が天候や稼働率に左右されません。
例えば、月額5万円の固定賃料でコインパーキング運営会社と契約すれば、年間で60万円の安定収入が確保されます。これにより、固定資産税や草刈りなどの維持費を賄えるだけでなく、黒字転換も期待できます。
狭小地や変形地でも対応可能
「農地は細長くて使いにくい」「変形していて建物は建てられない」といった場合でも、駐車場であれば柔軟に対応できます。コインパーキングは1台分のスペース(約2.5m×5m)から設置が可能なため、狭い土地や変形地でも活用事例が多くあります。
土地活用でお悩みなら、お気軽にご相談ください
農地を活用して駐車場経営を始めるならエコロパークにお任せ
農地をそのままにしておくと、維持費や管理の手間、さらには資産価値の低下といった問題がつきまといます。しかし、一括借り上げ方式の駐車場経営であれば、これらのリスクを回避しながら、毎月安定した収益を得ることが可能です。
エコロパークは、駐車場の企画から設置、運営・管理までを一貫して手がける専門業者です。
オーナー様の負担を最小限に抑える一括借り上げ方式を採用しており、初期費用なしで駐車場経営を始められるケースも多くあります。舗装工事や看板設置、精算機の導入などもエコロパーク側が対応するため、知識や経験がない方でも安心です。
また、狭小地や変形地、接道条件が限られた農地でも柔軟に対応できるノウハウがあり、土地に合わせた最適なプランを提案してくれます。放置農地を無理なく収益化したいと考えている方は、まずはエコロパークへ相談してみてはいかがでしょうか。
経験豊富なスタッフが、無料で現地調査や収支シミュレーションを行い、最適な活用方法をサポートします。
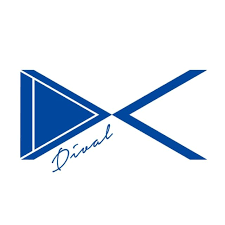
監修者
ディバルコンサルタント株式会社 代表取締役
明堂 浩治
芝浦工業大学 工学部 建築工学科卒。大手建設会社(大成建設グループ)にて、個人・法人地主への土地活用提案や建築営業に20年間従事。その後独立し、ディバルコンサルタント株式会社を設立。新築・改修工事、建物管理、土地の有効活用提案まで一貫したサポートを提供しており、特に相続後の土地や建物の活用相談にも多数の実績を持つ建築・不動産コンサルティングの専門家。
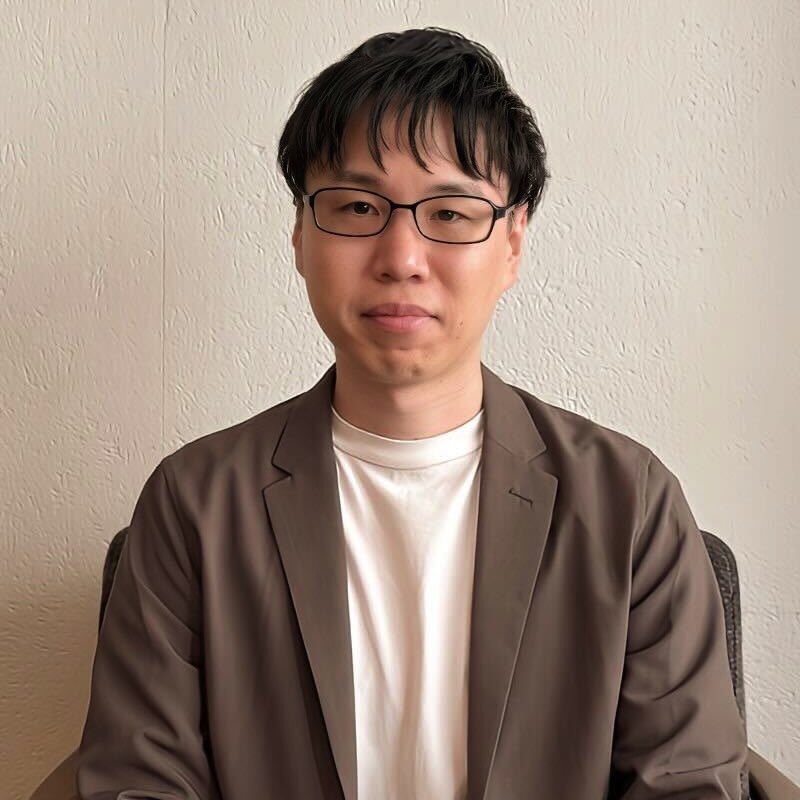
執筆者
株式会社スタルジー 代表取締役
飯塚 祐世
タワーマンションの理事長として、サブリース方式で空きが出ていた駐車場の収益改善に取り組み、修繕積立金不足の課題を解決。現在は、マンション管理組合向けの実践的サポートサイト「管理組合サポート」を運営し、現場目線での課題解決を行う。実体験に基づいた土地・建物の収益改善提案を得意とする、管理と経営に強い実務家。