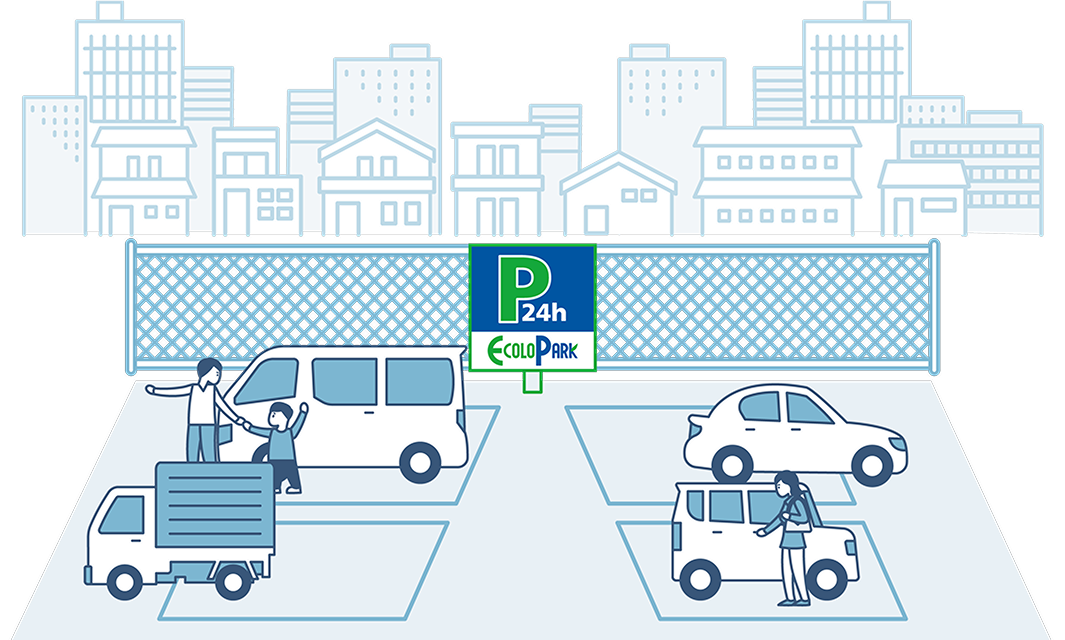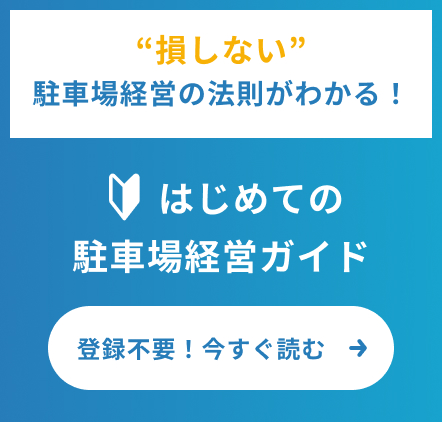空き家の解体費用は誰が払うべき?平均金額や安く抑えるためのコツも紹介!

空き家の解体費用を誰が払うべき?リアルなケース別解説
空き家の解体費用を誰が負担するべきか、初めてのケースでは分からない方がほとんどだと思います。
本記事では、それぞれのケースにおいて、誰が空き家の解体費用を負担するのかを解説していきます。
空き家の解体費用は、基本的には所有者が解体費用を負担するのが原則です。
ただし、相続放棄をした場合など、各ケースによって誰が負担するかは異なります。
以下に、主なケースと解体費用を負担する対象者を解説していきます。
ケース1:相続した実家などの空き家がある場合→相続人が解体費用を負担する。
ケース2:相続放棄した実家などその空き家がある場合→相続財産管理人が負担する。
ケース3:不動産売買における古家付き土地の場合→購入した現所有者が負担する。
ケース1:相続した実家等の空き家がある場合
基本的に相続人が解体費用を負担します。相続によって空き家を取得した場合、相続人とは遺産の相続権を有する者で、相続権順によって以下の順番となります。
- 配偶者
- 子・孫・ひ孫
- 両親・祖父母
- 兄弟・おい・めい
上記は民法で定められています。最終的には遺産分割協議により相続人を決めます。
ケース2:相続放棄した実家等の空き家がある場合
相続した空き家を相続放棄することも可能です。
その場合は、家庭裁判所にて相続財産清算人を選任する必要があります。
相続財産清算人とは、相続人がいない場合や相続放棄をした場合に、亡くなった人の財産を管理・清算する役割を担う人のことをいいます。
相続財産精算人に財産を引き渡すまでは、相続放棄をした人にも空き家の管理義務が発生しますが、解体費用を負担する必要があるかどうかについては、明確な法的ルールは定められていません。
ケース3:不動産売買における古家付き土地の場合
この場合は、原則として古家の解体費用は購入した現所有者が負担します。
※ただし、売買契約書に売主が解体する等などの特約がある場合はこの限りではありません。
古家付き土地の物件の場合は、買主が売買後に建物を解体する前提で購入するケースが大半です。また、解体費用に加えて、家具・残置物等の処分費用が別途発生する点にも注意が必要です。
空き家の解体にかかる費用はいくら?具体的な相場を解説!
解体費用は、空き家の延床面積や建物の構造等によって異なります。
相場は以下のとおりです。
- 木造:3~5万円/坪
- 鉄骨造:5~7万円/坪
- 鉄筋コンクリート造:6~8万円/坪
たとえば、木造2階建て・延床面積100㎡(約30.25坪)の場合、解体費用は一般的に90万円〜150万円程度となります。
※平屋の場合、立地や周辺状況等によっては、費用が増加することがあります。
解体費用をできるだけ安く抑える方法-補助金などをうまく活用しましょう-
自治体によっては、空き家を解体する際に利用できる補助金制度があります。うまく活用することで、解体費用の負担を抑えることができます。
補助金の額は自治体ごとに異なるため、事前にホームページなどで確認しましょう。一般的には、解体費用の20〜50%程度が支給されますが、上限金額が100万円に設定されている自治体が多く見られます。
また、補助金の申請は解体前に行う必要があり、自治体の年度内予算が無くなり次第、受付が終了となるため注意が必要です。
空き家の解体費用の捻出方法と捻出できなかった場合の対処法
空き家の解体にはまとまった費用がかかるため、補助金を活用してもなお負担が重いというケースも少なくありません。そのような場合には、以下のような選択肢も検討する価値があります。
- 相続人同士で空き家を相続する人を話し合いで決める。
- 空き家ごと不動産を売却する。
- リフォームして賃貸する。
- 空き家の解体ローンを組み、費用を借入する。
- 自分で空き家を解体し、費用を抑える。
- 相続放棄する。
このように、費用の捻出が難しい場合でも、複数の現実的な選択肢があります。それぞれのメリット・デメリットをよく理解し、最適な方法を見つけていきましょう。
空き家を自分で解体することは可能?知っておくべき法律と注意点
解体費用を抑えるために、自分で空き家を解体することは可能なのでしょうか。
結論から言えば、法律上は可能ですが、負担の大きさを考えるとおすすめはできません。
解体業者が解体工事を行う際には、建設業許可や解体工事業登録が必要です。しかし、個人が自分で解体工事を行う場合には、原則としてこうした許可は不要です。
とはいえ、建物解体に伴う産業廃棄物の分別や処理作業は、専門知識や設備がないと非常に困難です。さらに、建物を解体した後は、1ヶ月以内に法務局で建物滅失登記を行う必要があり、登記に関する知識も必要となります。
手間や時間効率を考えると、空き家を自分で解体し、登記まで行うことは現実的にはおすすめはできません。
空き家を解体するメリットとデメリット
空き家を解体するかどうかを判断するうえで、以下のようなメリット・デメリットがあります。
空き家を解体するメリット
- 家の倒壊リスクや防犯リスクが減る。
- 土地の有効活用が可能になる。
- 維持管理の手間やコストの削減ができる。
空き家を解体するデメリット
- 解体費用がかかる。
- 減税措置が受けられなくなり、固定資産税が増える。
- 建物としての売却や賃貸ができなくなる。
- 解体後の土地が売れにくくなる可能性がある。
空き家を解体する際は、固定資産税の増額に特に注意が必要です。
住宅用家屋が建っている場合は、住宅用地に係る特例によって固定資産税は最大1/6、都市計画税は最大1/3に軽減されています。
しかし、空き家を解体して更地にすると、本特例が受けられなくなり、固定資産税が最大で3〜4倍に増額される場合があります。
※実際の増加幅は、土地の評価額や建物の評価額によって異なります。場合によっては更地の方が税額が下がることもあります
解体によるコスト削減や土地活用の可能性とあわせて、税負担の変化も必ず検討しておきましょう。
空き家の解体手続き時に起こるトラブルや気を付けるべきポイント
空き家の解体手続きにおいて、もっとも起こりやすいトラブルは、親族間での解体費用の負担の議論、解体の実施そのものについての意見対立です。
経済的な理由から負担をしたくない、親戚付き合いが希薄である、親戚間の関係が悪い、など様々な理由から解体費用の負担をめぐって揉めるケースがあります。
対処法としては、まず解体費用を具体的に算出し、その金額に付いて親族間で相談することが重要です。
また、空き家の解体に反対する親族がいるケースもあります。空き家の解体では、相続権者が複数いる場合、相続人全員の合意が必要となります。相続権者の中に、建物に思い入れのある人がいて、空き家の解体に反対する場合もあります。
このような場合には慎重な話し合いが必要ですが、最終的には遺産分割協議を経て、相続者となった者の判断で解体を進めることになります。
また、解体工事の際には、近隣住民とのトラブルが発生する可能性もあります。
解体工事では、騒音・振動・ほこりの飛散などにより、近隣住民に迷惑をかけることがあります。そのため、解体工事前には必ず近隣への挨拶を行い、解体工事の日程や作業時間帯等を説明し、理解と協力を得ることが大切です。
さらに、空き家の解体作業により、近隣の建物にヒビが入るなどの影響が出ることも稀にあります。そうした不安がある場合は、事前に近隣建物の写真を撮り、解体による影響の有無を確認できるようにしておくと安心です。
土地活用でお悩みなら、お気軽にご相談ください
空き家を放置するとどうなる?放置リスクと将来的なトラブル
空き家を放置するとどのようなリスクがあるのでしょうか?
結論からお伝えすると、デメリットを感じる面がほとんどです。空き家の放置は、所有者にとって金銭的・法的なリスクを伴うだけでなく、近隣住民とのトラブルの原因にもなりかねません。そのため、空き家をそのまま放置することは、所有者にとっても地域にとっても得策とはいえません。
どのようなリスクがあるか、解説します。
①空き家の老朽化・倒壊が起こる恐れがある
適切な維持管理がされていない空き家は、経年劣化が進行し、倒壊のリスクが高まります。また、屋根や外壁の一部が飛散し、通行人がケガをしたり、隣家に被害を与えたりするリスクもあります。
②維持費がかかる。(固定資産税・火災保険料・草刈り等)
建物が存在する限り、建物の固定資産税などの費用が発生します。また、草刈りを怠ると雑草が生い茂り、害虫や害獣が住みつく可能性があるため、定期的な草刈りや敷地管理などの維持費が必要になります。
③不法侵入、不法投棄、犯罪に使用される治安上のリスクがある
管理されていない空き家は、不審者の拠点になったり、犯罪の温床となったりするおそれがあります。また、敷地内にゴミを不法投棄されるといったトラブルも発生しやすく、近隣の住環境に悪影響を及ぼします。
④特定空家に指定される
「空家等対策の推進に関する特別措置法」の設定により、特定空家に指定された場合、対応を怠ると過料の対象となったり固定資産税の軽減措置を受けられなくなる可能性があります。また、行政指導に従わない場合、行政代執行により強制的に空き家を解体され、解体費用を請求されます。
そもそも空き家を相続した場合、何から始めるのか
空き家を相続した場合、まず遺産分割協議を行い、相続人が決まったら相続登記を行います。
相続登記とは相続した不動産の所有権を前の所有者から相続人に移転させる手続きのことです。
相続人が複数の場合、空き家の解体をするか否か、解体費用をどう負担するか、相続人全員の合意が必要です。なお、誰が解体費用を支払うのかは法的に決まっていません。
一般的には法定相続分によって費用負担の割合を決定する場合が多いですが、最終的には相続人同士が話し合って決める必要があります。
相続人が複数人いる場合、遺産分割協議で空き家をどのように相続するか話し合いが必要になってきます。相続人全員の同意が必要で、協議が難航するケースも多いので注意が必要です。
協議が完了したら遺産分割協議書を作成し、遺産分割を行います。
相続登記は法務局で手続きを行います。自分でも手続き可能ですが、負担を考えると司法書士に依頼するケースが多いです。
なお、2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内に相続登記を行わないと罰せられる可能性があります。
所有権を移転させた後は、空き家の活用方法を検討します。
例えば、空き家の活用には以下の方法があります。
- 売却:空き家を売却する。
- 賃貸:賃貸物件として貸し出す。
- 居住:自分自身や家族が居住する。
具体的な手続きや空き家に関する法律や固定資産税について
空き家で住んでいなくても、建物の固定資産税・都市計画税はかかります。
なお、住宅用家屋が建っている場合は、住宅用地に係る特例で土地に係る固定資産税は最大1/6、都市計画税は最大1/3に軽減されています。
先述した通り、空き家を解体すると固定資産税が高くなる可能性があることに注意が必要です。詳しい計算は専門家にお願いすると良いでしょう。
また、近年の法改正により、空き家の管理義務や税制面での影響がさらに強化されています。2023年12月に空家等対策の推進に関する特別措置法(空家等対策特別措置法)が改正されました。
この法律において倒壊の危険性が高いなど、周囲に著しく悪影響を及ぼす(特定空家)に指定された場合、対応を怠ると過料の対象となったり固定資産税の軽減措置を受けられなくなる可能性があります。
行政指導に従わない場合、行政代執行により強制的に空き家を解体され、解体費用を請求されます。
空き家を相続放棄した場合の解体費用はどうなるのか
相続放棄をする場合、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。相続放棄をすると遺産のプラスマイナス共に放棄となり、その後は相続放棄の撤回はできません。
相続権のある空き家を相続人全員が相続放棄した場合、相続の対象となる空き家は最終的に国のものとなります。その場合、家庭裁判所で相続財産清算人を選任する必要があります。
相続財産精算人に財産を引き渡すまでは家の管理義務が発生しますが、相続放棄をした人が解体費用を負担する必要性については明確なルールはありません。
最終的には家庭裁判所が選任した「相続財産精算人」が解体費用を負担します。
空き家の解体業者を探している方や費用を抑えたい方必見!エコロパークで土地を有効活用しませんか
空き家を解体し、駐車場にするには以下のメリットとデメリットがあります。
空き家を解体し、駐車場経営を始めるメリット
- 駐車場に転用する初期費用が安い
- 駐車場の維持費が安い
- 賃料収入を得られる
- 後々の転用性が高い
- 駐車場の運営会社に管理を委託できる
空き家を解体し、駐車場経営を始めるデメリット
- 固定資産税が高くなる可能性がある
- 空き家の解体費用がかかる
- 税金の優遇措置を受けられない
エコロパークでは空き家の解体業者の紹介からはじまり、完全借り上げでのご契約で初期費用0円、管理費用が0円となるメリットがあります。初期費用を抑え、安定した収入確保が可能です。
相続した空き家の維持には、固定資産税等がかかりますが、駐車場経営によって固定費を補填し、土地を有効活用できます。
空き家として放置した場合の建物倒壊リスク、雑草や不法投棄、犯罪の温床になるといった近隣住民に迷惑をかけるリスクを低減できます。
また、エコロパークでは、キャッシュレス精算機を導入することで、効率的な経営管理が可能になります。他の土地活用方法に比べ、駐車場経営はメリットが多いです。
まずはお気軽にエコロパークにご相談ください。
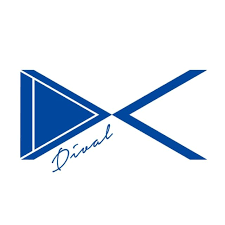
監修者
ディバルコンサルタント株式会社 代表取締役
明堂 浩治
芝浦工業大学 工学部 建築工学科卒。大手建設会社(大成建設グループ)にて、個人・法人地主への土地活用提案や建築営業に20年間従事。その後独立し、ディバルコンサルタント株式会社を設立。新築・改修工事、建物管理、土地の有効活用提案まで一貫したサポートを提供しており、特に相続後の土地や建物の活用相談にも多数の実績を持つ建築・不動産コンサルティングの専門家。
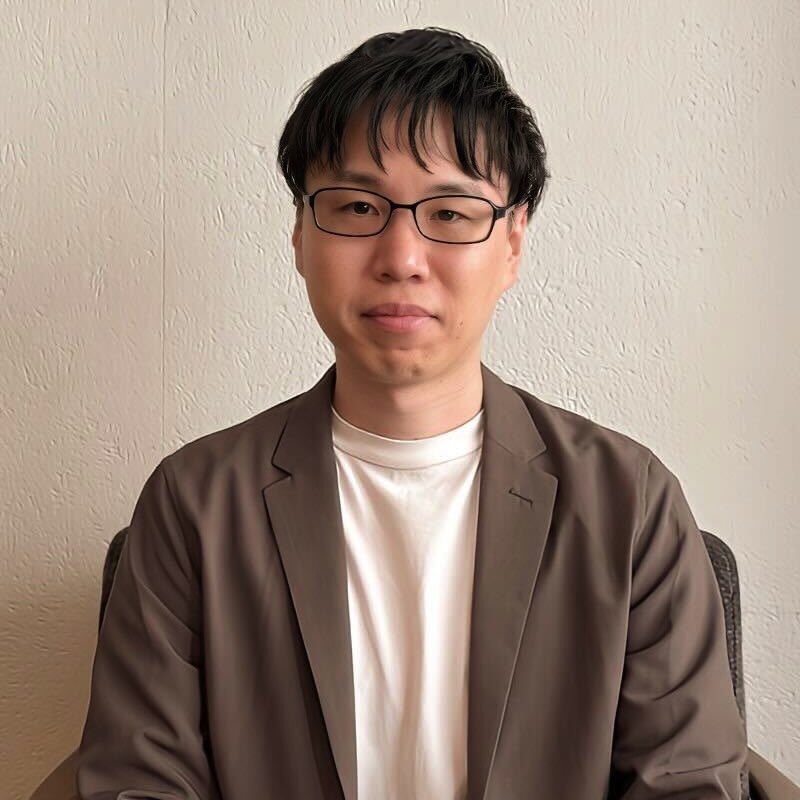
執筆者
株式会社スタルジー 代表取締役
飯塚 祐世
タワーマンションの理事長として、サブリース方式で空きが出ていた駐車場の収益改善に取り組み、修繕積立金不足の課題を解決。現在は、マンション管理組合向けの実践的サポートサイト「管理組合サポート」を運営し、現場目線での課題解決を行う。実体験に基づいた土地・建物の収益改善提案を得意とする、管理と経営に強い実務家。